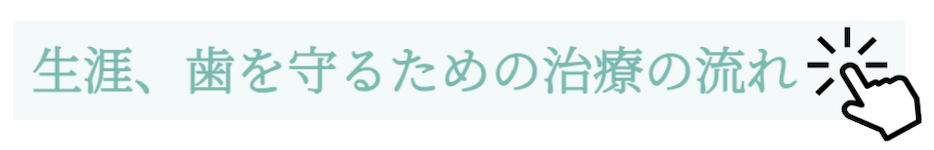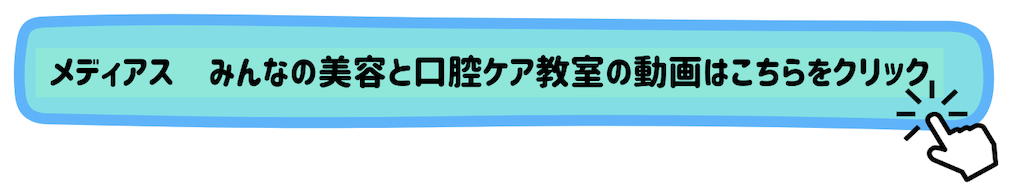2025-08-11 スタッフBlog
夏バテだけじゃない?「お口の夏バテ」にも要注意!歯ぐきや唾液に起こる変化とは
暑さが年々脅威を増し、ここ数年は「酷暑」とさえ言われるようになりました。そんな環境の中、だるさや食欲不振などの「夏バテかもしれない」という症状を感じる方も多いのではないでしょうか。
夏バテはさまざまな体の不調を引き起こしますが、実は口腔内にもあらわれる場合があります。
本日は、「お口の夏バテ」についてお話しします。
目次
夏バテの症状はお口にも出る!
夏バテは暑さによって体の状態が変化し、恒常性を保てなくなることで不調があらわれますが、実は口腔内にもその変化が起こっています。
暑さによる口腔内の変化として、代表的なものをご紹介します。
1.水分不足による唾液の減少
暑さで体内の水分が不足すると、唾液の分泌量が減少します。
唾液は口腔内を殺菌する役割があるため、唾液の減少によって細菌が繁殖しやすくなり、口臭やむし歯、歯周病、口内炎、ドライマウスなどのトラブルが発生しやすくなります。
暑さによる水分不足ももちろんですが、現代ではエアコンの利用による冷えがきっかけで血行不良となり、唾液の分泌量が減少するケースも少なくありません。
2.免疫力の低下
高温多湿な日本の夏は、体力を消耗しやすく、自律神経の乱れや免疫力の低下を引き起こします。
免疫力が低下すると細菌に対する抵抗力が弱くなり、やはり口腔内のさまざまなトラブルにつながりやすくなります。
唾液の減少と併せて考えると、「細菌が増えやすくやっつけにくい」という状態が起こるのです。
3.食生活の変化
夏は炭酸飲料やスポーツ飲料などを飲む機会が増えます。
また食欲がわかずにさっぱりしたものが食べたいと、お酢や柑橘類が登場することもあるのではないでしょうか。
これらのものは全て酸性の食品であり、摂取する量などによっては酸蝕歯といわれる、酸によって歯のエナメル質が溶けてしまう状態になることがあります。
酸蝕歯になると、知覚過敏になったり、むし歯になりやすくなったりします。
これらの症状が出ることを「お口の夏バテ」といいます。お口の夏バテは全身症状の夏バテと違い、だるさや食欲不振などの自覚しやすい症状として出ないため、気づいた時には進行してしまっていることも。
そのため、日ごろからの予防がとても大切になります。

「お口の夏バテ」を防ぐには
予防が肝心になるお口の夏バテ。具体的にはどんなことをすれば良いのでしょうか。
1.水分補給
第一に、水分補給は何よりも大切です。
「喉がかわいた」と感じてから水分を摂ると、既に体内は乾燥している状態ですし、クーラーの効いた部屋にいると、喉のかわきを感じづらくなる傾向にあります。
そのため、常に水分を携帯、もしくは近くに置き、「喉がかわく前に水分補給をする」というのを心がけると良いでしょう。
カフェインには利尿作用がありかえって体内の水分を追い出してしまうため、水かノンカフェインのお茶などがおすすめです。
2.丁寧な歯みがき
夏バテによる倦怠感などによって、つい歯みがきも億劫になりがちです。
しかし夏の口内環境は特に乱れやすいため、その一息の頑張りが大きな差になります。特に口内がすっきりすると、だるかった気分も少し軽くなる感じがするのではないでしょうか。
自分に合った歯ブラシを使って磨き、歯間ブラシやデンタルフロス、マウスウォッシュなども活用すると良いでしょう。酸性のものを良く飲んだり食べたりする方は、フッ素入りのアイテムを取り入れることを検討できるとなお良いです。

夏には特に気を付けたい歯周病!歯医者を賢く頼る手段も
「お口の夏バテ」についてご紹介しましたが、お口の夏バテは自覚症状として現れづらい分、気づいたら進行してしまっていたというケースも少なくありません。
特に歯周病については、30代以降の3人に2人は罹ると言われており、「国民病」と呼ばれるほど身近でありながら自覚症状が出づらく、重度になってから受診する方も後を絶ちません。
そのためこの夏をきっかけに歯医者を受診し、早めに「お口の夏バテ」対策ができると良いでしょう。
平均寿命に比べて約20年短いと言われる、歯の寿命。かかりつけの歯医者がいると、定期健診やメンテナンスなどを通じて、より良い口内環境と、健やかな歯を保つことができます。

いのうえ歯科クリニックでは、適切な検査や治療はもちろんのこと、教育を受けた専任の衛生士がメンテナンスを行っており、幅広い知識の元で安心して通っていただける医院づくりをしています。
あなたの大切な歯を、一緒に守っていきましょう。