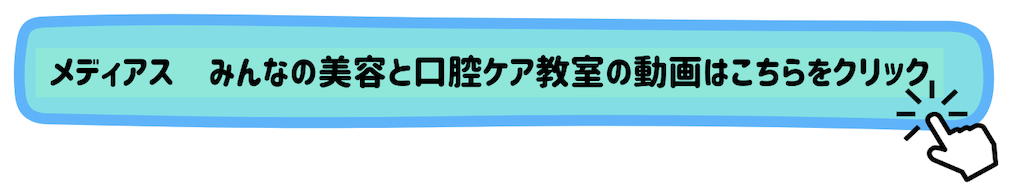2025-01-09 スタッフBlog
歯周病とストレスの意外な関係!原因と予防策を解説
目次
歯周病とは?
歯と歯茎(歯肉)の隙間(歯周ポケット)に細菌が侵入すると、歯肉の炎症が起こります。この炎症が進行すると歯を支えている骨を溶かしてしまい、歯がぐらついたり、抜けてしまったりすることもある病気を歯周病といいます。
歯周病は身近な病気で、日本人における成人のうち、約80%の方がかかっていると言われています。
歯周病の原因には大きく分けて細菌因子、宿主因子、環境因子という3つの危険因子があり、ストレスは環境因子に分類されます。
細菌因子はプラーク中の細菌のことで、歯周病の原因になるものとして、P.g.菌(Porphyromonas gingivalis)、T.f.菌(Tannerella forsythensis)、Td.菌(Treponema denticola)、P.i.菌(Prevotella intermedia)、A.a.菌(Actinobacillus actinomycetemcomitans)などがあることが判明しています。
また、宿主因子は遺伝的要素や年齢、歯の残数、糖尿病への罹患有無などが関係してきます。
ストレスは、環境因子にあたります。

歯周病の原因
歯周病の直接的な原因は歯垢で、ブラッシングが充分でなかったり、砂糖を過剰に摂取したりすると溜まります。
また歯周病を進行させる因子としては、糖尿病、喫煙、歯ぎしり・食いしばり、歯の不整合、糖尿病、骨粗鬆症などの疾患、ストレス……などが挙げられます。
本日は、多くの方にとって身近な存在である、ストレスと歯周病についてお話しします。

歯周病とストレスの関係性
一般的に強いストレスが加わると、自律神経のバランスが崩れ、本来体に備わっている免疫力が低下することで、さまざまな影響を及ぼします。
歯周病も影響を受けるもののひとつです。ストレスが大きいと交感神経が過剰に働くことにより、ねばねばした唾液を多く分泌する唾液腺(舌下腺、顎下腺)が刺激され、口の中の水分が相対的に少なくなります。唾液の中には歯周病菌に対する免疫物質である、リゾチームやラクトフェリン、免疫グロブリンなどの物質が含まれていて抗菌性を発揮するため、その働きが弱くなってしまいます。口腔内がねばつくとむし歯になりやすいことは比較的知られていますが、歯周病が進行する原因にもなります。
また、交感神経と副交感神経のスイッチが上手くできないことで、睡眠が浅くなり、睡眠の質が低下します。これにより、歯周病が進行する因子である歯ぎしりや食いしばりが誘発されやすくなることも分かっています。
歯ぎしりや食いしばりは、歯に不自然な強い力を加えることになるため、口腔内にダメージを加えてしまい、歯周病による歯周組織の破壊と同様のことが起こります。それによって、歯周病が進行してしまうのです。
また、歯ぎしりや食いしばりは、夜だけでなく日中にも無意識に意識に行ってしまうことがあります。日常的に歯ぎしりや食いしばりをしてしまうことで、歯周病が進行しやすくなってしまうのです。
また、歯周病によって歯周病菌が口腔内に増えることで、血液や胃等にも入り込み悪影響を与えます。ストレスでこの免疫力が落ちると、より歯周病が発症・進行する可能性が高くなります。

ストレスが原因の歯周病を予防するには?
ストレスを溜めない生活ができるのが1番ですが、現代社会に生きている以上、なかなかそういうわけにもいきません。そのため、ここでは対症療法についてお伝えします。
日中の歯ぎしり、食いしばりについては、気づいた時に力を抜くことを心がけるほか、耳下腺のマッサージをして緊張した筋肉をゆるめつつ、唾液の分泌を促すことも有効です。飴やガムなどでも、唾液の分泌を促すことができます。
また、夜間の歯ぎしり、食いしばりについては、マウスピースを装着する方法もあります。マウスピースは歯科医院で作製してもらえるため、一度かかりつけの歯科医に相談してみるのも良いでしょう。

ストレスは万病の元ですが、歯周病においても最大の要因となります。心配な方は、ぜひかかりつけの歯医者で歯周病検査を受けてみてください。
いのうえ歯科クリニックでは、適切な検査や治療はもちろんのこと、教育を受けた専任の衛生士がメンテナンスを行っています。
定期的なメンテナンスを通じて、平均寿命に比べて約20年短いと言われる、歯の寿命を伸ばす取り組みを行っています。歯周病に負けずに大切な歯を、一緒に守っていきましょう。
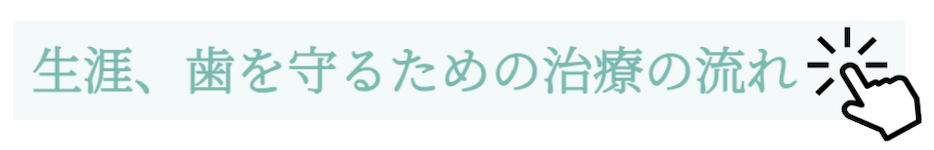
-
2025.07.01
7月休診日のお知らせ
今月の休診日は、毎週日曜日、木曜日です。 21日(月)は祝日(海の日)のため、休 […]
-
2025.07.17
ずっと通える歯医者さん、どう選ぶ?東海市でライフステージ別に考える“わが家のかかりつけ“
「最も頻繁に通う病院」がどこかと考えたとき、歯科を思い浮かべる方が多いのではない […]

2025.07.17
ずっと通える歯医者さん、どう選ぶ?東海市でライフステージ別に考える“わが家のかかりつけ“
「最も頻繁に通う病院」がどこかと考えたとき、歯科を思い浮かべる方が多いのではない […]
-
2023.09.26
『みんなの美容と口腔ケア教室』を開催しました!
9月19日に『みんなの美容と口腔ケア教室』を開催いたしました! 参加者は11名で […]