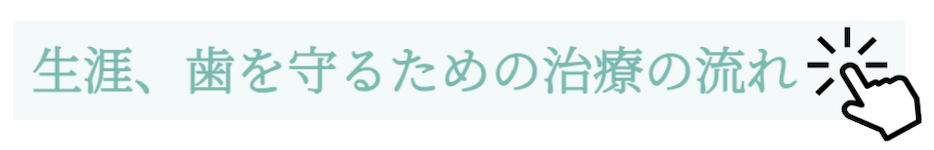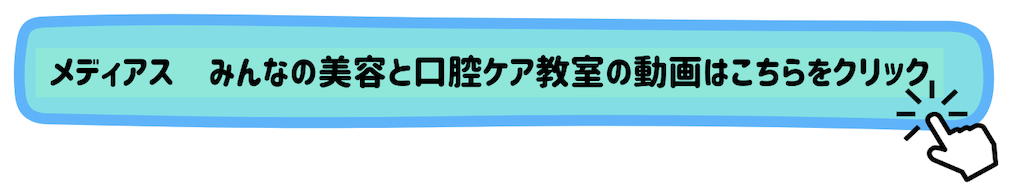2025-09-09 スタッフBlog
季節の変わり目に歯が痛いのはなぜ?考えられる原因と歯科での対処法
目次
季節の変わり目になると歯が痛くなる!?
日本には春夏秋冬の四季もさることながら、「立春」「春分」「立夏」「夏至」など、24もの季節を表す言葉である「二十四節気」というものがあります。
日本はそれだけ1年を通して気候の移り変わりと、それに伴う気温や湿度、気圧などの変化も大きいという特徴があります。
その気象条件の変化に体が対応しきれないことで起こるさまざまな不調のことを「気象病」と言いますが、実はその気象病によって、歯の痛みやお口のトラブルが引き起こされることがあります。
特に季節の変わり目に起こりがちな気象病ですが、その原因と対策について、本日はお伝えします。

気象病とは?
改めて気象病とは、気圧、温度、湿度などの変動によって起こる不調全般のことをいいます。
天気の悪い日に片頭痛が起こったり、古傷が痛んだり、だるくて起きるのがつらかったり、妙にイライラしてしまったり……という経験はないでしょうか。
これらは全て気象病のひとつと考えられ、特に季節の変わり目で気候の変化が大きな時に起こりやすくなります。
他にも気象病として考えられるものに、以下のものが挙げられます。
・頭痛
・関節痛
・過去に怪我をした箇所の痛み
・肩こり、腰痛
・耳鳴り
・めまい
・倦怠感、疲労感
・吐き気
・手足のしびれ
・むくみ
・気分の落ち込み、不安感
・イライラ
これらの症状は、気候の変化に体が適応しきれないことで、自律神経の乱れを起こすために発生します。
自律神経が乱れると体にさまざまな影響を及ぼすことは広く知られていますが、そのトリガーのひとつとして、季節の変わり目などの気候の変化があると考えられています。
気象病を自覚した経験がある方は日本人の約70%、気象病によって生活に支障が出たことがある方は約40%といわれ、日本に住む私たちにとって気象病は身近なものといえます。

歯が痛いのも気象病が原因かも?
そして季節の変わり目などに、歯の痛みや口腔内の不調を感じる方も実は多くいらっしゃいます。
気圧の変化によって、歯の内部にある歯髄腔内と言われる部分の空気や体液が膨張し、神経を圧迫して痛みが生じることがあります。この痛みのことを「気圧性歯痛」もしくは「航空性歯痛」といいます。
気圧性歯痛(航空性歯痛)は、季節の変わり目だけではなく、雨などの悪天候の時や、飛行機に乗った時、標高の高い場所に行った時、スキューバダイビングをしている時など、気圧の変化を感じる場所でも同様に起こる可能性があります。
気圧性歯痛が起こるのは、むし歯などの炎症がある歯、治療済みで詰めものや被せものをしている歯など、口腔内で既往となる箇所が多く、感じ方は「ズキズキ」とした痛みであることが多いです。

気圧性歯痛が起こったら
気圧性歯痛を感じたら、まずはすぐに歯医者を受診しましょう。
なぜなら気圧性歯痛が健全な歯で起こるリスクは低く、むし歯や歯周病が進行しているサインである可能性があるからです。
気圧性歯痛の原因となるむし歯や歯周病などを治療することで、再発がしづらくなるでしょう。
しかし最初にお伝えしたように、日本は気候の変化が激しい環境下にあります。
そのため、もちろん自宅での適切な歯みがきや口腔ケアも大切ですが、歯医者での定期健診やメンテナンスを通じて根本的に歯の健康を保つことで、原因となるむし歯や歯周病を長期にわたって予防することが可能です。
定期的に通うのが苦にならず、相談のしやすい「かかりつけ」を、この機会に見つけてはいかがでしょうか。

いのうえ歯科クリニックでは、適切な検査や治療はもちろんのこと、教育を受けた専任の衛生士がメンテナンスを行っており、幅広い知識の元で安心して通っていただける医院づくりをしています。
あなたの大切な歯を、一緒に守っていきましょう。